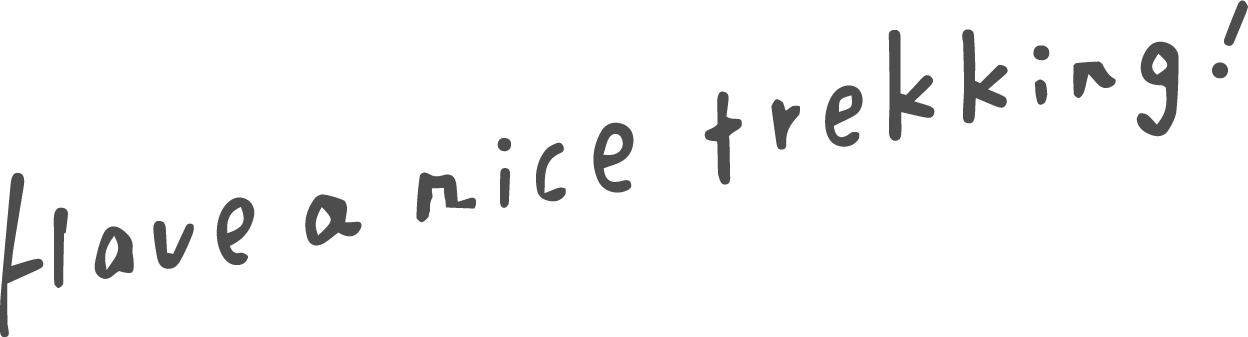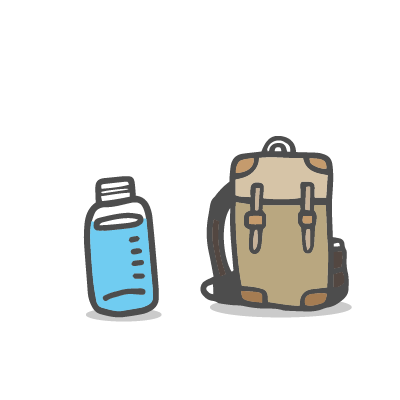Event Overviewぐんま山フェスタ開催概要
| 日 時 | 2025年10月18日(土)・19(日) 9:00~16:00 |
|---|---|
| 会 場 | ビエント高崎 エクセルホール他 |
| 主 催 | ぐんま山フェスタ実行委員会 |
NEWSお知らせ
- 2025.9.7ぐんま山フェスタ2025 メインコンテンツ ステージイベントゲスト発表!
- 2025.7.162025年10月18(土)・19(日)にぐんま山フェスタ2025の開催が決定しました!
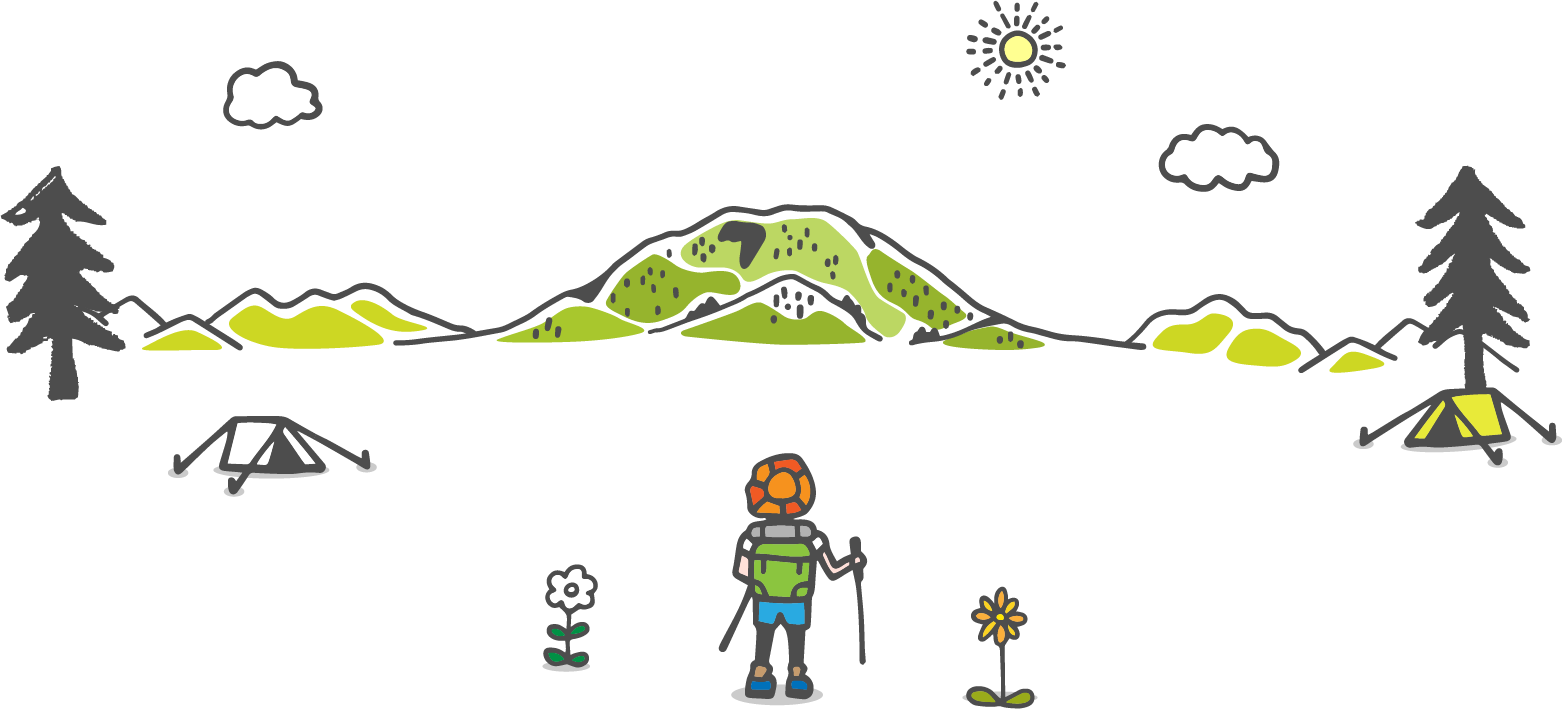
ABOUTぐんま山フェスタについて
私たちの暮らす群馬県には、人々を魅了してやまない
数々の名峰や豊かな自然があります。
これは間違いなく他にはない「群馬の財産」です。
そんな素晴らしい群馬県の山々や周辺の魅力をもっと多くの方々に
知ってもらいたいという思いから生まれた「ぐんま山フェスタ」。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
ぐんま山フェスタ実行委員会



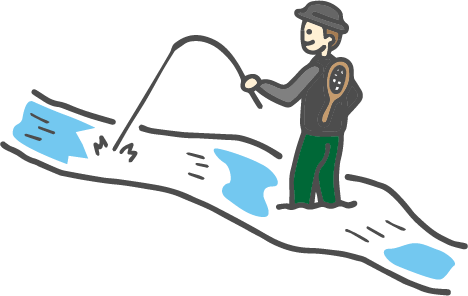
STAGE EVENTステージイベント

登山YouTuber かほ トークショー
ぐんま山フェスタ2025 メインコンテンツ発表!
あの登山YouTuberのかほさんがぐんま山フェスタに来ます。
是非皆さまお楽しみにご来場ください。
【登山YouTuber かほ トークショー】
日程 :10月18日(土)
時間 :①10:00~10:45
(受付開始 9:30~)
②14:00~14:45
(受付開始 13:30~)
入場料:無料(50席)
※※注意点※※
・50名様(座席分)は整理券が必要となります。
・整理券はPeatixにて【9/19(金)12:00~】申し込みを行います(先着順)。 申し込みはこちら
・50名申し込みされた時点で終了となります。
・座席順は当日の受付順とさせていただく予定です。※会場は30分前に開場予定。
・午前・午後の両方の申し込みは不可とさせていただきます。
・座席周辺での立ち見はエリア内でしたら可能です。
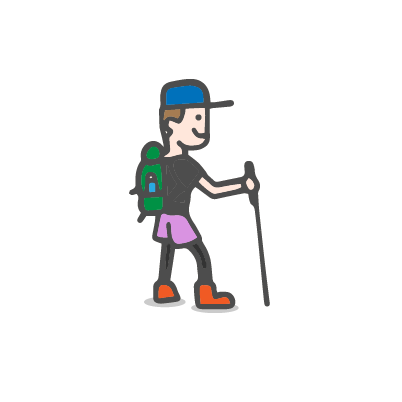
AREA/SPONSERエリア情報・協賛一覧
エリア情報
※順不同
協賛一覧
- アミノバイタルⓇ
- 石井スポーツ高崎店
- BMZテクニカルサポート前橋
- 希望食品株式会社
- 社会福祉法人チハヤ会 MAKIT
- 山とスキーの店 石井DreamBOX
- 生活協同組合パルシステム群馬
- 田中商店
- ヘルシーパル赤城
- 株式会社ジーオーエヌ
- 草加煎餅本舗きらく
- かたしな高原スキー場
- 道草屋
- MANABAR
- 車の解体工場株式会社ギヤ
- DANG SHADES
- ユニバーサルスポーツ協会
- UKULERIYA
- 創業慶應二年太田旗店
- サイトウグンマ
- Luna rainbow Outdoor Academy
- ココヘリ
- 株式会社ヤマテン
- 谷川岳ヨッホ by 星野リゾート
- SHOPCAFE Qu
- 公益社団法人群馬県緑化推進委員会
- PRIRET
- FIAT・ALFA ROMEO
- 富士スバル株式会社
※順不同
特別協賛一覧
※順不同
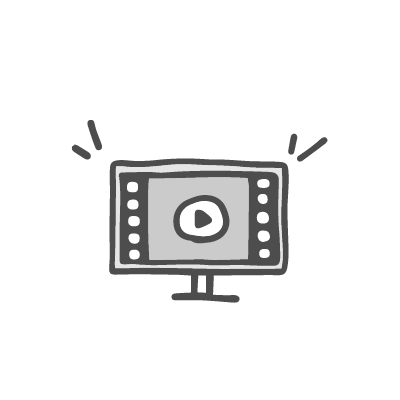
PR MOVIE観光動画紹介
各市町村の観光動画や自然をご覧になれます。
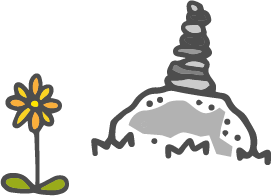
東吾妻町

【公式】真田氏上州の拠点岩櫃

まちづくり推進課東吾妻町役場
長野県 山ノ内町

Nature Tour in Snow Monkey Town Yamanouchi

Explore Snow Monkey Town Yamanouchi in Autumn

Explore Snow Monkey Town Yamanouchi in Winter
みかぼ森林公園

ブナの樹幹流

テン

カエデ

鹿

伊香保森林公園

二ホンアナグマ

リス

二ホンカモシカ

アカゲラ
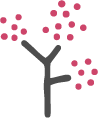
たのしい山登りを!